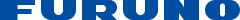- ホーム
- 車両管理ソリューション
- コラム
- なぜあなたの「荷待ち時間対策」は進まないのか? バース予約受付システムではなく、「事業所内の滞在時間を正確に把握したい」という事業者が増えつつある理由
コラム・物流百景
なぜあなたの「荷待ち時間対策」は進まないのか?
バース予約受付システムではなく、「事業所内の滞在時間を正確に把握したい」という事業者が増えつつある理由
「物流の2024年問題」から始まった物流クライシス対策として、工場や物流センターなどでトラックドライバーが拘束される荷待ち・荷役時間の削減が喫緊の課題となっています。これに呼応するように、2024年公布、2026年春に施行される新物効法では、1運行あたりの荷待ち・荷役時間を2時間以内に収める「1運行2時間ルール」が発動します。
こういった背景から、古野電気には「当社の工場や物流センターなどにおけるトラックの滞在時間を計測したい」という問い合わせが増えているんだとか。
このあたりの事情に詳しい方は、「滞在時間だけ計測してもねぇ?」と疑問を感じるかもしれません。
本記事では、荷待ち・荷役時間の削減問題を考えつつ、トラックの滞在時間を計測したいという問い合わせが増えている理由を解き明かしましょう。
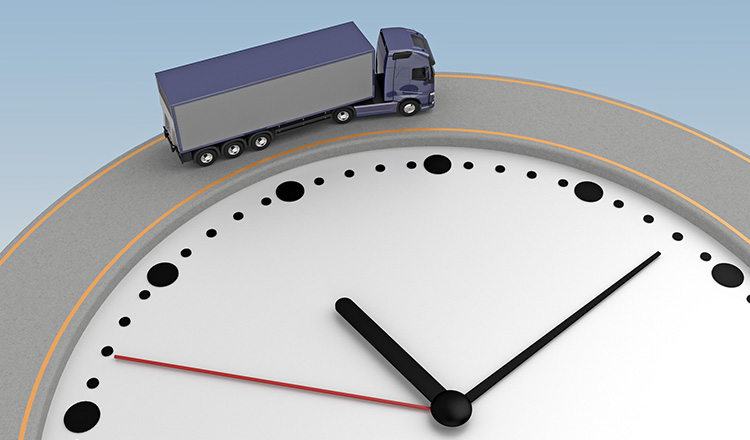
荷待ち・荷役時間が削減されるのは、レコーディングダイエット効果
筆者は、複数のバース予約受付システムの導入事例を執筆した経験があります。
その経験から、荷待ち・荷役時間が削減されるのは、レコーディングダイエット効果だと考えています。
実は筆者、導入事例取材を行う前は、「バース“予約”システムならばともかく、バース“受付”システムでは、荷待ち・荷役時間の削減効果は出ないだろう」と考えていました。
ちなみに、バース“受付”システムとは、トラックが工場・物流センターなどに着車した際、受付をするシステムであり、従来の紙ベースの受付票をデジタル化したものを指します。
対して、バース“予約”システムとは、バース受付システムの機能に加え、あらかじめトラックが着車する時間を予約するためのシステムを指します。
実際には、ほとんどのシステムは、バースの受付機能に加え、時間予約機能も備えていますから、より正確に解説すると「バース予約受付システムの受付機能しか使っていない現場」「バース予約受付システムの予約機能も使っている現場」という表現が正しいです。
ちなみに、古野電気のソリューション「FLOWVIS(フロービス)」は入退場管理システムです。これらの違いは、過去の記事『「誰でも分かる」「イチから分かる」バース予約システム・トラック予約受付システム・車両入退場管理システムの違いを解説」』をご確認ください。
| システムの種類 | 主な特徴 | 手軽さ (導入コスト) |
自動化・省人化 の度合い |
|
|---|---|---|---|---|
| バース予約システム | バースを予約することで、入出荷を行う時間枠を予約できるシステム | ◯ | △ | |
| トラック予約 受付システム |
バース予約を含んだ入出庫に関する包括的な業務を管理するシステム | ◯ | △ | |
| 車両入退場管理システム | 車番認識 | カメラで車両ナンバーを読み取ることによって、工場・物流センターなどの敷地内を出入りする車両を記録するシステム | △ | ◯ |
| ETC 認識 |
ETC車載器の電波信号(固有ID)を読み取り、入退場する車両を記録するシステム | △ | ◎ | |
話を戻しましょう。
あらかじめ、「『◯◯行きの貨物を集荷するトラックが、午前9:00に着車する』と分かっているのであればともかく、『トラックが着車しました』ということを記録するだけで、荷待ち・荷役時間の削減が実現するのかな?」と筆者は疑問を感じていたわけです。
しかしバース予約受付システムを導入した複数の事例を取材するにつれ、むしろ受付機能しか使っていない現場のほうが高い効果を得ていて、逆に予約機能も使っている現場では、十分な荷待ち・荷役時間の削減効果が出ていないケースがあることを知りました。
レコーディングダイエットとは、定期的に体重を計測・記録することで、食事制限や「運動しなきゃ!」という当人の危機意識を刺激し、改善意欲を高める減量手法です。
当然、計測・記録することで満足してしまう人には効果がありませんが、バース予約受付システムにも同様のことが言えることに気がついたのです。
なぜ、バース“受付”システムの方が、荷待ち・荷役時間の削減効果が出るのか?
一般論として、導入事例記事はソリューション導入のBefore/Afterを比較します。当然、この落差は大きければ大きいほど導入効果を強く読者に訴えることができます。
しかし、バース予約受付システムの導入事例取材では、Before、つまり導入前の荷待ち・荷役時間を把握していないケースが多くありました。
筆者が取材した、メーカーの物流子会社D社もそうでした。
D社では、ある時、全社的に荷待ち・荷役時間削減に取り組むことを社内方針として定めました。そこで、D社のS営業所では、紙ベース受付票を毎週、Excelに転記して荷待ち・荷役時間を把握し始めました。当時のS営業所の担当者は、「当営業所で、ときに3時間近くもの長い荷待ち・荷役時間が生じているとは思いもしませんでした」と振り返っていました。
反省したS営業所では、荷待ち・荷役時間の削減に取り組み始めました。
荷待ち・荷役時間の集計結果を事務所に掲示し、月曜日の朝礼では、荷待ち・荷役時間が長時間化している理由について、所員全員でディスカッションを行ったのです。
すると改善対策がいくつか挙がるようになってきました。
- 3か所あるバースを、入庫専用、出庫専用に分けること
- 入庫バース、出庫バースの横に貨物の一時置きスペースを用意すること
このような対策をした結果、荷待ち・荷役時間を30分以内に抑えることができるようになりました。
S営業所ではバース予約受付システムを導入しましたが、それは手書き伝票をExcelに転記するのが面倒だったからです。
一方、D社ではS営業所の成功事例を受け、全営業所にバース予約受付システムの導入を開始しています。しかし、すべての営業所でS営業所のような導入削減効果が出ているわけではありません。
残念ながら、バース予約受付システムを導入しただけで、改善行動を起こさない営業所もあるからです。
なぜ、バース“予約”システムだけでは駄目なのか?
実際のところ、予約機能を使えば、理論上は待機時間をゼロにすることも可能です。
予約時間に入出庫作業を開始すれば、(荷役時間はともかく)荷待ち時間はゼロにできるからです。
新物効法上の1運行2時間ルールでは、工場・物流センター側の都合で待機させた時間のみを荷待ち時間としてカウントし、運送会社・ドライバー側の都合で発生した時間はカウントしないことを基本としています。
一方、運送会社側は予約時間に遅刻しないようにするために、30分程度の余裕を持って現地に到着、工場・物流センター周辺の路上などで待機しているケースが少なくありません。時間帯で予約できる(例えば9:00~9:30など)予約機能の使い方をしているところであれば問題は少ないのですが、それでも予約時間がある限り、「遅刻したらまずい」という運送会社・ドライバー側の焦りを完全に拭い去ることは難しいからです。
こうなると工場・物流センター側は、バース予約受付システムの予約機能を使うことで、見かけ上は荷待ち時間がゼロにすることができます。結果、「荷待ち時間を減らさなければ!」というモチベーションが働きにくくなってしまうのです。
加えて、前述のとおりバース予約受付システム導入前の荷待ち時間の実態を把握していない現場も多く、こうなると荷待ち・荷役時間削減へのモチベーションが、さらに働きにくくなってしまいます。
バース予約受付システムを導入して、荷待ち・荷役時間の削減に取り組む事業者の特徴
ある意味、筆者の「バース“予約”システムならばともかく、バース“受付”システムでは、荷待ち・荷役時間の削減効果は出ないだろう」という考えは間違いではありません。
荷待ち・荷役時間の本質的な削減を実現するのであれば、その原因を取り除くことが必要です。荷待ち・荷役時間の発生原因は、貨物の積み卸し作業などの庫内業務にあるのですから、その原因を追求し、業務プロセスを改善しなければなりません。
つまり、荷待ち・荷役時間の削減を実現するためには、以下の2つの取り組みを実施しなければなりません。
- 荷待ち・荷役時間を把握・分析し、それぞれの発生原因を究明すること
- 発生原因に対処する改善活動を実施すること
バース予約受付システムは、受付を記録し、荷待ち・荷役時間を計測するだけです。
「発生原因を究明する」ためには、あくまで関係する工場・物流センターの担当者らが自発的に取り組まなければなりません。
一方で、バース予約受付システムを導入し、荷待ち・荷役時間の本質的な削減に取り組んでいる事業者もちゃんといます。
例えば、トラックを1日チャーターで運行している事業所です。
こういった事業所では、バース予約受付システムの予約機能では把握できない隠れ荷待ち時間も含めてトラックの実走行時間を増やし運行効率を改善する必要があるからです。
また荷待ち・荷役時間問題の本質を理解している事業所も同様です。
先の隠れ荷待ち時間の存在を問題視し、その改善が必要なことを理解している事業所では、バース予約受付システムにおける予約機能のジレンマに気づいており、かつ本質的な改善に取り組んでいます。
対策を行わないと、運送会社やドライバーから、「あの事業所は、結局待たされるんだよな」と嫌われてしまうことをきちんと分かっているのでしょう。
そもそも、バース予約受付システムはドライバーが恣意的に受付(入場)と終了(退場)の操作を行う必要があり、実際に事業所の構内に滞在していた時間とはズレが生じる可能性が拭えません。さらに言うと、特に終了(退場)操作については、失念するドライバーもいますから、その正確性・信頼性は劣ります。
その点、事業所の入退場門などに設置されたカメラやETC認識装置で機械的にトラックの入退場を記録すれば、事業所内での滞在時間は正確かつ確実に測定できます。
バース予約受付システムではなく入退場管理システムを求め、古野電気に「当社の工場や物流センターなどにおけるトラックの滞在時間を計測したい」と問い合わせを行う事業者は、本稿につらつらと書いてきたような「バース予約受付システムが抱えるジレンマや課題」を理解しているのでしょう。
物流クライシス対策に求められる、法対応に留まらない本質的な改善活動
物流クライシスに対する危機感から、政府は物流革新政策を進め、昨年(2024年)は貨物自動車運送事業法と物効法の改正を、今春は貨物自動車運送事業法のさらなる改正とともに、新法である「貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律案」を公布しました。
これは必要なことですし、また評価されてしかるべき政策です。
しかし一方で、物流革新政策の本質的な意義を理解することなく、「罰せられないように法対応すれば良いんでしょう!?」と安直な対応をする事業者も増えています。
一方で物流革新政策に右往左往することなく、本質的な物流改善に取り組んでいる事業者は、本稿で取り上げたように「トラックの滞在時間を計測したい」と考えるのでしょう。
これも情報過多社会が生んだ弊害なのでしょうか。
「なぜ今、物流を改善することが必要なのか?」、この本質を理解し安直な取り組みに流されてしまわないよう気をつけたいものです。
記事のライター

坂田 良平氏 物流ジャーナリスト
Pavism代表。「主戦場は物流業界。生業はIT御用聞き」をキャッチコピーに、執筆活動や、ITを活用した営業支援などを行っている。ビジネス+IT、Merkmal、LOGISTICS TODAY、東洋経済オンライン、プレジデントオンラインなどのWebメディアや、企業のオウンドメディアなどで執筆活動を行う。TV・ラジオへの出演も行っている。
※本文中で使用した登録商標は各権利者に帰属します。
ピックアップ
コラム一覧
物流百景
- 生成AIが注目される今だからこそ、物流業界におけるAI活用を考える(ライター:坂田良平氏)
- 【2026年4月施行】「1運行2時間ルール」は事実上の義務化! その課題と本当に取り組むべき荷待ち・荷役時間削減のポイントとは(ライター:坂田良平氏)
- なぜあなたの「荷待ち時間対策」は進まないのか? バース予約受付システムではなく、「事業所内の滞在時間を正確に把握したい」という事業者が増えつつある理由(ライター:坂田良平氏)
- DX時代だから考えたい「部分最適化でしかないソリューションベンダー」とより良いパートナーシップを築くために必要なこと(ライター:坂田良平氏)
- トラックドライバーの個人所有スマホに業務用アプリケーションを導入?ソリューションベンダー側の課題と責任を考える(ライター:坂田良平氏)
- 物流DXは、バズワードからいよいよホンモノへ【国際物流総合展2024で感じた兆し】(ライター:坂田良平氏)
- 難敵!、国際物流総合展の歩き方(ライター:坂田良平氏)
- 「誰でも分かる」「イチから分かる」バース予約システム・トラック予約受付システム・車両入退場管理システムの違いを解説(ライター:坂田良平氏)
物流百景
物流百景
- 生成AIが注目される今だからこそ、物流業界におけるAI活用を考える(ライター:坂田良平氏)
- 【2026年4月施行】「1運行2時間ルール」は事実上の義務化! その課題と本当に取り組むべき荷待ち・荷役時間削減のポイントとは(ライター:坂田良平氏)
- なぜあなたの「荷待ち時間対策」は進まないのか? バース予約受付システムではなく、「事業所内の滞在時間を正確に把握したい」という事業者が増えつつある理由(ライター:坂田良平氏)
- DX時代だから考えたい「部分最適化でしかないソリューションベンダー」とより良いパートナーシップを築くために必要なこと(ライター:坂田良平氏)
- トラックドライバーの個人所有スマホに業務用アプリケーションを導入?ソリューションベンダー側の課題と責任を考える(ライター:坂田良平氏)
- 物流DXは、バズワードからいよいよホンモノへ【国際物流総合展2024で感じた兆し】(ライター:坂田良平氏)
- 難敵!、国際物流総合展の歩き方(ライター:坂田良平氏)
- 「誰でも分かる」「イチから分かる」バース予約システム・トラック予約受付システム・車両入退場管理システムの違いを解説(ライター:坂田良平氏)