建設DX関連記事
【連載】AIの活用でDX推進を成功に導く②
~AIでできること、できないことを知る~
AI導入で適切且つ期待された効果を得るためには、クライアント企業が抱える課題を整理することがカギであると、前回の記事(【連載】AIの活用でDX推進を成功に導く① ~自社業務のブラックボックスは何処にある?~)で、株式会社エクサウィザーズ社の直野廉氏と、川西亮輔氏は強調されていました。そのことから、AIを導入検討する際は、AIでできることと、そうでないことを知っておく必要があります。引き続き建設DX編集部が伺いました。
AIのポイントは、「適切な指示」を与えること。適切な課題設定はそのためにも必要
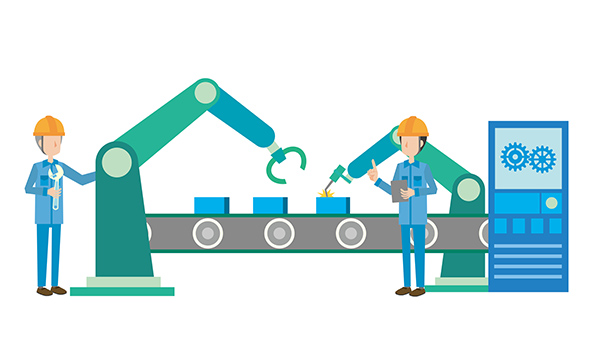
編集部:具体的に、AIができることはどんなことでしょうか?
直野氏:例えば製造業だと、「工場の任意のラインがいつ頃に壊れそうだ」といった故障の予兆を捉えることに使われます。これまでだと、現場で10年程働いている方の経験で、「そろそろ何か起きそうだ」と感じる、いわゆる第六感的なことが、AIで実現可能です。10年経験のある方も、ただそう思ったわけではなく、これまでの経験の積み重ねがそう思わせるのです。
ではその経験値が何かというと、蓄積されたそれまでの現場データなどで、意外に多いのが天気や気温、湿度などの外乱による影響です。こうしたさまざまな情報をもとに人間が学習した結果の集合体が第六感となり、同じようにデータを集めていくことで、人が得られる判断や、それに基づく制御などができていくのかな、と思います。
川西氏:身近で例えると、人間でいうところの「脊髄反射」的な働きが、今のAIが得意としているところです。例えば、人間は猫の写真を見た時、それが猫だと認識するまでに思考を挟んだりしませんよね。こういう形で耳があって、毛が生えていて…なんて考えず、見た瞬間に「猫だ」と認識します。
AIもこうした脊髄反射的な簡易判別や、結果が明確な問題設定に対して、それまでの経験などを学習させることで理解できるようになります。このように、人間でいうところの脊髄反射レベルが今のAIで実現できることで、おそらく最も使われている機能と思われます。
編集部:何となく分かる気がしますが、具体的に情報として「何を」提供すればよいのでしょうか?
直野氏:重要なのは、指示する際に「AIにこういうふうに学習してほしい」ということを、人がきちんと定義した上でデータを集めていくことです。つまり、データ自体の質と量が重要になってきます。ただひたすらデータを集めればいいというわけではなく、解決したい課題に対して適切な質と十分な量のデータを揃えることが必要です。人間が、「このデータはこの答えに強く結びつく」と思い込んでいても、解析してみると何の関係性もなかったといった結果になると、AIでは解けなくなります。
編集部:では、AIができないことは何でしょうか?
川西氏:基本的に人間でも判断が難しいものは、当然AIにも学習させることができません。シンプルに言うと、答えを事前に用意できない問題は学習させることができず、人間が設計できる範囲を超えるものは、AIにはできません。
そういう意味でも、前回(【連載】AIの活用でDX推進を成功に導く① ~自社業務のブラックボックスは何処にある?~)申し上げたように、「課題設定を明確にしましょう」というのが私たちの立場です。「何を」アウトプットしたいのかが分からなければ、当然AIを作ることはできません。あとは、その答えにたどり着くのに必要な情報を持っているかどうか。この部分がとても重要です。
熟練技術を可視化して平準化する基盤は「ノーコード」で提供
編集部:御社を通じてAIを導入したいという企業は、どういった分野が多いのでしょうか?
直野氏:製造業のお客さまが目立ちますね。業界で言うと、三品業界と呼ばれる化粧品や医薬品に食品業界。それ以外ですと、鉄鋼や建設業界など幅広くお仕事をさせていただいております。
我々の特徴としては、一般的にAIで解決できる領域の、さらに難しいところをやっていく点です。工場のライン職長さんや、重機を使うような現場で働く親方さんが備え持つ「カン」と「コツ」をどうにかして見える化、もしくは自動化したいといったご要望が来たときに我々が出動するのです。そういう意味では、業種業態問わず日本の製造業を支えておられる方々のサポート、ということになりますね。
編集部:2022年8月末には、「カン・コツ」の可視化に関わるサービスをリリースされていますね。
直野氏:はい。人手不足に悩む製造現場など、熟練の技術を要して属人化してしまった作業を可視化することで、技能の継承に役立てるサービスです。熟練技能者が言葉にせずとも体現している技術、いわば「暗黙知」とされていた部分を、さまざまなデータを集めてAIで「形式知」化、つまり見える化することを支援しています。
具体的にどのようなことをするかというと、熟練の技術を可視化したり自動化したりする上で必要なデータを、実際の熟練技能者の動きからセンサーなどを活用して集めます。そしてデータ処理を行うことで、熟練の技術を構成する要素が何なのかを見出します。使い道としては、例えば建設業界ならば、重機を動かす上で個人の「カン・コツ」に相当する部分を平準化することで、効率的で安全な作業に役立てられます。あるいは、製造業ならば製造ラインの制御条件を自動で最適化できます。
このサービスの基盤としているのが、当社のAI・DXプラットフォームexaBaseです。そこには、当社がこれまで500社超に提供してきた技術アセットが蓄積されています。
ここで掲げている技術は、大きく分けて5種類ほどあります。これまでお話しした「(1) 可視化」のほかに「(2) 予測」、これは例えばデータをもとに来月のある店舗の売り上げを予測するなどです。また「(3) 予兆」として、工場などのセンサーデータを元にした異常検知の傾向を捉えます。それから「(4) 最適化」。例えば物流企業の受注データを元に、運送のトラックをどう動かせば効率良く配達できるかなどです。またこのほかに、「(5) 分類」があり、ノーコードで提供しています。
編集部:ノーコードとなると、お客さま側としては「何をやっているのか分からない」といったブラックボックス化がなくなるということですね?
直野氏:ブラックボックス化の問題は、どの企業も大きいのだと我々も身に沁みて感じております。答えを導き出すというお題であれば、ディープラーニングなどを活用してその答えを出すのは得意なのですが、お客さまにはその過程が見えないため不安なのです。そうなると、先に進みづらくなります。
お客さまご自身の肌感覚として、成功体験を得たいという面もあります。業界に関係なく多くの企業に共通の課題なのかなと思いますが、そういう意味では、現場の方も納得感を得ながらDXに進んでいくということが重要なのかな、と考えています。
ビフォー:実は誰かが、工程の「差分」を埋めている? アフター:平準化
 (左)直野氏、(右)川西氏
(左)直野氏、(右)川西氏
編集部:日本人のコミュニケーションは非常にハイコンテクストで、言葉で表現されていない部分も相当あると言われていますが、そういった文化的な難しさはありますか?
直野氏:よくあるシチュエーションでは、製造業のお客さまで工場が複数箇所にまたがり、且つその本社の方がDXを導入しに入ってくるときですね。同じ会社でも、工場の生産管理部門の方や現場の方、また本社の三部門では、日常会話で使う用語やケアするポイントが微妙に異なっていることがあります。
例えばエンジニアと営業が同居するミーティングでは、両者が齟齬なく理解できる用語を用いて会話する必要がありますが、両者がお互いに認識の異なった用語や話し方をすると少しずつ視点にズレが生じ、打ち合わせの最中に社内の人同士で会議が始まったりすることが往々にしてあります。「それ、どういう意味ですか」とか。こうした問題はAIに行く手前の話ですが、大事な要素ですね。これまで日本では、「阿吽(あうん)の呼吸」を良しとする傾向があり、いま述べたようにさまざまな部署の方が関わってくると、生じやすい状況かと思われます。基本的な概念として、プロジェクト進行のあり方を知っていただくことは重要なのかなと思います。例えば「このペットボトルを持ってください」と言うと、人によって持ち方が違うかもしれません。ボトルのどの部分を、どのように持つのかまで指示してあげないと、少しずつズレが生じます。ここはまさにプロジェクト進行における要点です。
編集部:多くの人が働く現場ではどうしても、暗黙の内に共有されているルールも存在します。その意味ではAIとの親和性はどうなのでしょうか?
直野氏:暗黙のルールの下でうまく進んでいるように見えていても、実際には誰かが「差分」を吸収しているパターンを見かけます。悪く言えば、誰かが割を食っているのです。
「記録には書かれていないけれど、しょうがないな、多分こういうことだろう」と思って直してくれる人がいることが多いのです。よく拝見するお客さまの現場例では、金属部品を製造する工程において、出来上がった部品にバラツキがあるので、それを汎用機にロボットアームでピックしたいと言うご相談を受けます。そもそもなぜ部品にバラツキが起こるのかを調べていくと、対象ピック工程の前工程において、設計図面に対して出来た製品のどこに不良があったのかをチェックし、その後に加工するといった工程があることが分かりました。そして、そのチェック方法が人によってペケマークであったりマルマークだったりと異なり、その一方で不良の位置やサイズまできっちり書いている人もいるのです。つまり、記録にバラツキがある状態です。
その次の工程ではチェックのあった部分を研磨したりするのですが、担当する方の目線によって「多分、ペケマークの付いている箇所はキズがあったのだろう」と、独自の判断で肉盛りをしてみたり、またチェックの付いていないポイントでも、人によって不良に対する閾値が違うので、自分の基準で追加したりすることもあると伺います。このような感じで、実は帳尻合わせしてる人がいるのです。
さらに問題なのが、一見問題なく進行しているように見える状態が一番危ないのです。その差分を吸収していた人が配置転換などで居なくなると製造ラインが崩壊してしまうからで、「急に品質が下がったけど何故だろう?」ということが起きます。状況を掘り下げてみると、あまり重要視されていなかったポジションの方が一人居なくなっていて、その方が実は潤滑油になっていたということがよくありますね。
編集部:そういう部分にAIを上手く導入して平準化につなげるのですね。
直野氏:はい、まさにその通りです。
記事のライター

石野 祥太郎 建設DXジャーナル初代編集長/古野電気株式会社
無線の技術者として新技術や製品開発に従事、建設DXの社内プロジェクトを推進
※本文中で使用した登録商標は各権利者に帰属します。
建設DXに関するご相談・お問い合わせ
関連リンク
建設DX Journal
2024年の記事
-
スターリンクで建設現場のネットワークが快適に ~導入のメリットや、検討すべきポイント~
-
建設現場は屋外環境? ~電波のルールを正しく理解して使うには~
-
建築現場に無線ブロードバンド環境をつくり、建設DXを実現
-
LANケーブルを最小限に抑えて、メッシュWi-Fiを広範囲に展開 ~建設DXに向けた最新事例のご紹介~
-
建設現場向けWi-Fiシステムを活用した建設DXの実現
-
建設DXにおける業界潮流の変化と今後の展望を大予想
-
AR(拡張現実)導入を検討するために知っておくべきことは?
-
ICT機器の「天敵」現場の電磁ノイズ ~安心してICT機器を使うために、その正体を知ろう~
-
位置情報データから見る今後のビジネスのトレンドとは?
-
生成AIとビジネスの付き合い方をどうすべきか?
-
スポーツイベントのDXでアスリートを可視化!? ~階段垂直マラソンでICT技術を導入すると驚きの効果が~







