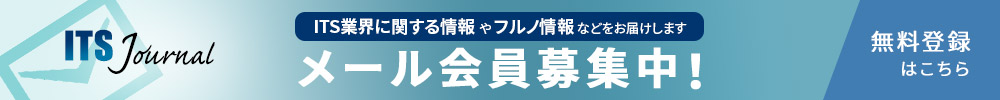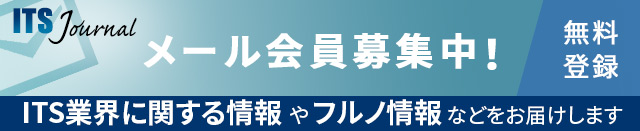ITS業界記事 Maas(モビリティのサービス化)の競争。技術分野ではM&A、協業が加速。~米CESレポート~
自動車産業界とCESの関わり方の変化
自動車産業界にとって毎年の恒例行事となった、米ラスベガスCES(Consumer Electronics Show:コンシューマ・エレクトロニクス・ショー)の時期がやってきた。
CESは、最新家電やIT関連メーカー、そして近年は自動車メーカー各社が次世代技術を披露する場として世界の注目を浴びている。
時計の針を少し戻すと、いまから20年ほど前の90年代後半、PC(パーソナルコンピュータ)の普及に伴い、PC関連のハードウエアやソフトウエアがCESの主役だった。そして2000年代中頃になると、タッチパネル式の電子端末機の初期型が登場し始めた。
さらに2000年代後半になると、スマートフォン時代へと突入。米グーグル(現アルファベットの系列会社)と米アップルの2強時代が始まり、スマートフォンありきの新しいビジネスモデルが次々と登場していった。
その過程で、自動車メーカーとCESとの関わり合いが変わっていった。
2000年代半ばまで、自動車産業にとってのCESは、カーオーディオやカーナビなど、いわゆる「アフターマーケット」での電気製品の出展の場だった。通信関連では、米ゼネラルモータース(GM)が、車載器システム(Embedded System)の「オンスター」を搭載した新車を発売しており、その販売促進の一環としてCESを活用していたに過ぎない。
そうした状況がスマホ登場によって大きく変わった。
当初は、車載データを自己診断システム「OBD(On-board diagnostics:オン・ボード・ダイアグノーシス)」の端子に小型通信器(通称ドングル《Dongle》)を取り付け、Bluetoothによってスマートフォンとデータを送受信する仕組みの商品が多かった。
その後、車載器とスマートフォンの直接的なデータ送信システムが登場。なかでも、スマートフォンの商品企画を先導できる立場のアップルとグーグルがそれぞれ、CarPlay(カープレイ)とAndroid Auto(アンドロイドオート)という独自プロトコルを確立した。
これに対して、自動車メーカー各社が参画するAGL(Automotive Grade Linux:オートモーティブ・グレード・リナックス)が、トヨタとリナックス協会の主導で立ち上がった。
トヨタ「e-Palette Concept」など、MaaS(モビリティのサービス化)での競争へ
車載器とスマートフォンとの連携が契機となり、コネクテッドカーのビジネス領域が一気に広がった。それまでコネクテッドカーといえば、車載器と道路インフラとの協調(V2I)や、車載器どうしの協調(V2V)が主流だったが、スマートフォンの登場がコネクテッドカーの考え方を大きく変えた。
こうしたコネクテッドカーと連動するように登場したのが、量産型の自動運転システムだ。2012年に欧米で自動運転の走行レベルの定義が決まったことで、自動車メーカー各社は各走行レベルの達成目標を公表するようになった。
そしてコネクテッドカーと自動運転の融合に加えて、昨今はジャーマン3(ダイムラー、BMW、VWグループ)による事業戦略である「EVシフト」が加わった。
さらには、Uber(ウーバー)やLyft(リフト)のようなライドシェアリングが欧米で急速に普及したことで、シェアリングエコノミーが次世代自動車ビジネスの大きな要因として浮上してきた。こうしたビジネスは、モビリティのサービス化としてMaaS(Mobility as a Service)と称されることが多い。
以上のような、コネクテッドカー、自動運転、EVという3つの技術領域がMaaSという事業領域へとつながっていく流れが、ここ数年のCESで体験することができた。
今回のCESで見ると、ダイムラーが2016年9月から始めた事業戦略「CASE」を強調した。CASEとは、Connected、Autonomous、Shared、Electricの頭文字だ。その上で、ダイムラーはMaaSの新規ビジネスについては明らかにしていない。
これは、米フォードも同様で、MaaS を「街づくり」という概念で紹介するに留めた。
一方、トヨタはMaaSの量産化計画を明確に示した。それが、商用向けの自動運転EVの「e-Palette Concept」だ。トヨタがコネクテッドカー、EV、自動運転の3つの技術をひとつのプラットフォームでまとめた製品である。今回の発表では、連携する企業として米アマゾン、中国のライドシェアリング大手のDidi Chuxing Technology(ディディ)、米宅配ピザ大手のピザハットなどが参画し、今後さらに参画企業が増える見込みだ。
技術分野では、ティア1のM&A、協業が加速
次世代自動車ビジネスにおいて今後、自動車メーカーでのMaaSの競争が激しくなる中、技術分野での競争の場は部品メーカーであるティア1に移った。
今回のCESで目立ったのは、中国のIT大手の百度(バイドゥ)が進めている自動運転事業「アポロ計画(Project Apollo)」だ。米エヌビディアなどが参画しており、ここに、変速機(トランスミッション)大手の独ZFが加わることが明らかになった。 また、米インテルは、走行している多数の車から単眼カメラ(Single Camera)で画像データを収集し、それをクラウドに送ることで自動運転に必要な地図を生成するシステムを、自動車メーカーや自動車部品メーカー向けに販売する計画を強調した。
この他、自動運転向けの地図データでは、車載器向けの大手である独ヒア(Here)に対して、これまでのジャーマン3とインテルに加えて、独ボッシュと独コンチネンタルも出資することになった。
こうした動きに対して、自動車部品大手の米デルファイは、自動運転ベンチャーのニュートノミー(nuTonomy)を買収し、デルファイ・オートモーティブをAPTIV(アプティブ)と社名変更した。同社の技術を搭載したBMWによる、ライドシェアリングのLyftとの協業も発表した。
このように、コネクテッドカー、自動運転、そしてEVやFCV(Fuel Cell Vehicle:燃料電池車)などの技術領域では今後、さらなる業界再編が進みそうだ。
記事のライター

桃田 健史氏 自動車ジャーナリスト
専門は世界自動車産業。その周辺分野として、エネルギー、IT、高齢化問題等をカバー。日米を拠点に各国で取材活動を続ける。
一般誌、技術専門誌、各種自動車関連媒体等への執筆。
インディカー、NASCAR等、レーシングドライバーとしての経歴を活かし、テレビのレース番組の解説担当。
海外モーターショーなどテレビ解説。
近年の取材対象は、先進国から新興国へのパラダイムシフト、EV等の車両電動化、そして情報通信のテレマティクス。
ITS製品・ソリューション
FURUNO ITS Journal
2024年の記事
2023年の記事
- 第1回「ジャパンモビリティショー」の現場で感じたこと
- 福島で考える「クルマと水素社会の未来」
- クルマが「V2Iで自走」する生産ライン ~トヨタ、モノづくりワークショップ2023~
- 新型ランドクルーザー「250」に見る、グローバルSUV市場の変化
- 賛否両論の新設「電動キックボード」 ~街づくりのためのデータマネージメントシステム~
- 「トヨタテクニカルワークショップ2023」の強烈インパクト ~進化する「3つの領域」と「大きな課題」~
- EVを活用した「エネルギーマネージメント」ビジネスの展望
- ホンダの次世代予防安全技術 ~ESV27取材を通じて~
- 日産の電動化戦略にみる、EV市場の今後 ~Nissan Futures Tech Seminarで「X-in-1」を世界初公開~
- 氷上で感じた、フィードフォワード型の最新姿勢制御システムの実力 ~日産のEVやe-POWERでe-4ORCEを試す~
- 2023年の自動車産業界は「迷いの年」になる?
2022年の記事
- モータースポーツを活用した「カーボンニュートラル」への試み~水素燃料車、次世代バイオディーゼル燃料車、カーボンニュートラル燃料車~
- 新発想の自動運転技術。ホンダ「CIマイクロモビリティ」とは~地図レス協調運転技術と、意図理解・コミュニケーション技術~
- 自動運転におけるSIP-adusの軌跡と大きな成果。~次期SIPへ~
- 物流業界で進むDX化 ~三菱ふそう「FUSO eモビリティソリューションズ」や、東海クラリオン「THE BOXシリーズ」に注目集まる~
- 「デジタル交通社会」の未来 ~「官民ITS構想ロードマップ」の大胆な書き換え~
- 新設されたADAS試験場を取材 ~自動車アセスメント(JNCAP)に新たなる動き~
- アップル次世代「CarPlay」登場。自動車産業への影響がさらに深まるのか?
- 新しい『官民ITS構想・ロードマップ』の在り方とは?~デジタル庁で始まる『人中心』『社会中心』の議論~
- 国が示す「現実的な」自動運転ロードマップと、最新スバルアイサイトXの体感レポート
- FCV(燃料電池車)は普及するのか? ~乗用より商用で、トヨタ・ホンダに新しい動き~
- 新車の“完全”オンライン販売が日本でもスタート。クルマの新しい買い方は定着するのか?
- 初披露が続々!東京オートサロン2022の現場レポート ~舞台裏を知る筆者が約40年の歴史を振り返る~
2021年の記事
- 2050年、グローバルで四輪車・二輪車「交通事故死者数ゼロ」へ ~ホンダの最新安全技術を体験~
- 常石造船の製造とDX。本社工場を単独取材
- 日本版スマートシティ、実用化に向けた新たな動き
- 自動運転バス(サービスカー)の“本格的”な実用化はいつ?
- クルマを使った災害時のデータ活用
- トヨタ主導のコネクテッド技術で商用車ビジネスが大きく転換~軽トラから大型トラック・バスまで~
- トヨタがコネクテッドカーで「パーソナライズ」事業参入
- ESG投資に振り回される、日本自動車メーカーのカーボンニュートラル戦略
- 最新型の自動運転・高度運転支援システム搭載車を乗り比べて感じたこと
- カーボンニュートラルでLCA(ライフ・サイクル・アセスメント)を強化する動きが加速か?
- 半導体不足で露呈した、自動車産業の実情
- 人材育成を目指す、オンライン自動運転コンテスト
2020年の記事
- 「2030年ガソリン車禁止」で変わる、CASEの行方
- 空飛ぶクルマは、本当に飛べるのか?
- 自動運転の「理想」と「現実」~中国から見える、日本にとっての大きな分岐点~
- SIP第二期、自動運転で重要性を増すV2X
- スバル「アイサイトX」の技術詳細 ~GNSSと高精度三次元地図などを活用~
- フランス車が人気。「ライフスタイル系」のブランド戦略
- いまこそ真価が問われる、「人中心」のスマートシティ/スーパーシティ
- MaaSやCASE、”コロナ後”の自動車産業はどう変わるのか?
- COVID-19で自動車・モータースポーツ産業にバーチャル時代到来
- EVシフトの動向と消費者ニーズ
- トヨタ、ADAS記者発表 ~「急アクセル時加速抑制」のアルゴリズムを無償公開へ~
- 2020年の日本自動車産業 ~3つのターニングポイント~
- 「ながらスマホ」と「レベル3自動運転」
2019年の記事
- モーターショーもビジネスモデルの転換期 ~東京モーターショーレポート~
- MaaSの事業化(マネタイズ)~ITS世界会議シンガポールをレポート~
- アンドロイド・オートモーティブ、V2Xに注目~独フランクフルトモーターショー2019をレポート~
- 自動車流通革命とDCM(データ・コミュニケーション・モジュール)
- コネクテッドビジネスや、ホンダが新たに提唱した「eMaaS」の可能性
- 5G実用化に向けたサービスが続々登場
- 交通事故多発で注目されるコネクティビティ技術
- 上海モーターショーをレポート ~SUV、EV、自動運転、5G~
- ドローンビジネス ~15分ビジネスやみちびきの活用~
- 「まちづくり」としてのMaaS (Mobility as a Service)、国家プロジェクトとして本格的に推進
- CES主催者「2020年代はデータ期」、米CESに見る自動車産業の変革 ~CES 2019レポート~
- 自動運転、コネクティビティへの時代変化の中で目指す「原点回帰」
2018年の記事
- プライベートカー向け自動運転レベルの新たな提案と、注目される5G技術
- EVの標準化へ。充電インフラで欧米と日中が対立 ~神戸EVS 31現地レポート~
- 自動車専用の輸送船の見学と最新型のハイブリッド車の試乗
- 企画段階の製品も展示。モビリティサービスを見える化した「トヨタ・モビリティ・ショールーム」を新設
- 地域住民が主導の「コミュニティ・カーシェアリング」の可能性
- CESアジア現地取材。自動車ショーから、自動車「データ」ショーへ
- 交通量や自車位置の測定など、路車間通信で各社が新たなる試み ~ITSアジアパシフィックフォーラム in 福岡~
- 相次ぐ自動運転中の事故。「責任はない」と主張する各社と、安全性の標準化動向
- 空飛ぶ車やMaaS(モビリティのサービス化)など、スイス・ジュネーブショーを取材
- EV普及に向けた各国の政策
- Maas(モビリティのサービス化)の競争。技術分野ではM&A、協業が加速。~米CESレポート~
2017年の記事
- 自動車業界のビッグデータ主導権争い。企業間の連携がますます重要に。
- 自動運転におけるコネクテッドカーと路車間通信
- ETCのこれまで、ETC2.0のこれから
- シェアリングエコノミーの急速発展 ~商用シェアリングや、市街地交通の地下化~
- 世界初。自動運転レベル3を認めたドイツ ~不透明なアメリカはリーダーであり続けられるか?~
- ITS EU 2017現地レポート ~進む自動運転、どうなるeCall~
- インフォテイメントからITSまで。競争領域が広がる車載ビッグデータの世界
- GTC(GPU Technology Conference)取材!AI(人工知能)のデファクトスタンダート化とは
- ルネサスの新たなる挑戦!「e-AIソリューション」と「ルネサス・オートノミー」
- 自動車産業は製造業からサービス業へ。ビッグデータが引き起こす組織改革
- ドライバーの高齢化と、日本国内での事故対策への動き
- アメリカで進む、ライドシェアリングと完全自動運転の融合
2016年の記事
- 準天頂衛星システム(QZSS)の概要と、東京オリンピックなど本格実用に向けた動き ~G空間EXPO 2016レポート~
- 日本の自動運転プロジェクト「SIP-adus」は大規模な実証実験へ。また、日本独自のV2X動向とは。
- 自動車メーカーも多数出展する国際福祉機器展!パーソナルモビリティでは、屋内外で共用するGNSS/IMES技術が広がるか?
- 「プロパイロット」や「アイサイト」等、日系メーカーがADASの強化に注力する理由とは?
- 自動運転の法整備に新たな動き。そして、テスラ事故を受けたモービルアイとの契約解消とは
- コネクテッドカーで拡がるサイバーセキュリティの議論と、トヨタ主導の車載向けOS「AGL」動向
- 自動運転の鍵「リアルな三次元地図」の構築へ!屋内は歩行者版デッドレコニング(PDR)?
- EVの影で、ジワジワと加速する中国「BAT」の動き
- 「テスラの技術の原点」台湾で進む、新交通システムの可能性
- ジュネーブモーターショーの“本当の注目”は、「歩行者保護」基準への対応強化
- 激化する、クルマの新たなるクラウド上の「プローブデータ・ビジネス」
- CES 2016 現地レポート「データサービスが自動車産業の主要な収益源になる日」
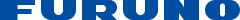


 メルセデスベンツとスマートを擁するダイムラー。最近の事業戦略の柱は「CASE」。
メルセデスベンツとスマートを擁するダイムラー。最近の事業戦略の柱は「CASE」。 トヨタの自動運転EV商用車、e-Palette コンセプト。
トヨタの自動運転EV商用車、e-Palette コンセプト。 中国のIT大手、百度(百度)も自動運転でのアポロ計画で出展。
中国のIT大手、百度(百度)も自動運転でのアポロ計画で出展。 車載器向けカーナビ地図の最大手、独HERE(ヒア)の展示。
車載器向けカーナビ地図の最大手、独HERE(ヒア)の展示。 デルファイ・オートモーティブから、アプティブに社名変更。自動運転関連企業の買収など進める。
デルファイ・オートモーティブから、アプティブに社名変更。自動運転関連企業の買収など進める。